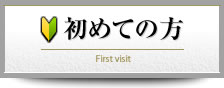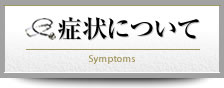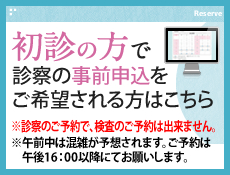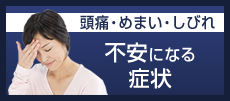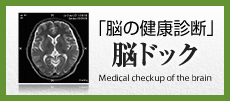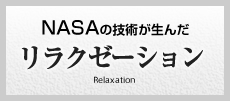妊娠中の抗痙攣剤の服用はこれらの薬の催奇形性から十分に事前の検討が必要です。一般的に全身痙攣等の発作の為に妊娠中や出産中に、胎児や母体に危険を引きこす可能性が抗痙攣剤の催奇形性を上まれば服用が許される事になります。具体的に考えれば正常な出産に際しての奇形の頻度は2~3%と考えられ、抗痙攣剤の種類によって異なりますが、最も安全とされる抗痙攣剤を服用してもこの頻度は2倍から3倍に増加するようです。従って妊娠中に抗痙攣剤を服用する事での奇形の頻度は4%~9%となります。つまり約1/11~1/25の出産で問題となる事になります。
一方、抗痙攣剤服用中でも痙攣発作(発作の重症度に関係なく)が1回以上/年起こる可能性のある症例では、薬を服用する事プラス発作の危険性の2重の問題から医師による妊娠許可の可能性は難しい事になります。
従ってより厳しく基準で症例を限定すると、癲癇の患者さんで痙攣発作のコントロールが3~5年間以上出来ており、なおかつ脳波が正常な症例で上記の内容を十分に理解された御夫婦に限り妊娠が許されると考えます。
何かと話題の脳脊髄液減少症(低髄圧症候群)は、以前には交通外傷後に起こるむち打ち症の原因ではないかと言われ、ブラッドパッチ(自己血を硬膜外注入)をする事で種々の臨床症状が改善する、いわば究極の診断及び治療法としてもてはやされた時期がありました。今は、その診断法や治療法に疑問視が投げかけられ(東京地裁H20.2.28等)、全ての症例でこの様な事はなく個々の症例で慎重に対処する事が重要の様です。私が個人的に関わらして頂いています交通外傷の事例や又は訴訟問題にも発展しかねない多くの事例は間違った知識と考え方が浸透している事が問題のようです。ここで改めてその知識を整理する意味から診断基準を列挙したいと思います。
日本神経外傷学会の診断基準(自動車ジャーナルNo1742-4頁)によりますと低髄圧症候群の「前提基準」を《起立性頭痛と体位による症状の変化》とし「大基準」を(1)《MRIでびまん性の硬膜の肥厚》、(2)《低髄液圧の証明》、(3)《髄液描出画像所見》としています。そして前提基準1項目+大基準1項目を満たす場合を低髄液圧症候群と診断しています。上記の起立性頭痛とは、坐位及び立位をとると15 分以内に増強するもので、外傷後30日以内に発症します(自動車ジャーナルNo1742-4頁)。
また問題点として、RI脳槽シンチに関してはアイソトープの吸収や排泄の早さに個人差があり、その診断価値はいまだ定まってない事(自動車ジャーナルNo1742-14頁)が挙げられます。従ってRI脳槽シンチは、将来的に上記の「大基準」(3)の内容の変更や、診断基準の大基準から省略される事があるかもしれません。
最後に。当たり前の話ですが、RI脳槽シンチの検査ではアイソトープを髄液内に注入する際に硬膜を穿刺針で破る為、検査後に髄液がもれることは当然の事です。問題はその様な漏れが、交通事故が原因で起こり、なおかつ持続的に髄液漏が起こる事により起立性頭痛が継続して起こっているかどうかが重要と考えます。