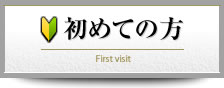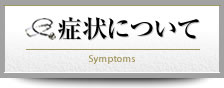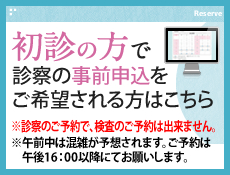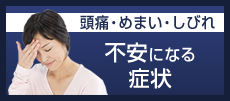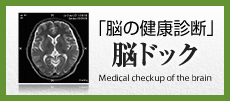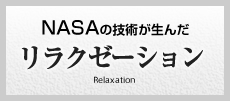高脂血症とは血液中のコレステロール値や中性脂肪の値が高い事を言います。コレステロールの中には、動脈硬化を予防する善玉コレステロールと動脈硬化を進行させる悪玉コレステロールがあります。高脂血症は、この悪玉コレステロール値が高いか、又は総コレステロール値が高い事を意味します。高脂血症等が原因で動脈硬化が進行すると様々な合併症を引き起こします。例をあげると脳梗塞等の脳卒中、心筋梗塞や大動脈瘤、腎機能障害や眼底出血等が代表的な疾患です。
高脂血症の原因には運動不足、食事の過剰な摂取や脂肪の取りすぎ、飲酒の他に、糖尿病、腎臓や甲状腺疾患等があります。また、女性の場合、閉経後にホルモンのバランスの関係から高脂血症になるケースもあります。
今回食事と高脂血症について述べたいと思います。高脂血症に対する食事療法の第1は適切なカロリーの食事にする事です。最近は食生活環境の変化で、インスタント食品や冷凍食品やファーストフード等で知らないうちにカコリーの高い食事を摂取している場合もあります。今一度、食事内容をよく考えて見ましょう。また油料理は1日2品までと決めましょう。肉よりも魚中心の食事内容にし、コレステロールの多い食品(霜降り肉、うなぎ、卵類)は避けましょう。食物繊維の多い野菜、キノコ、海草、こんにゃくはコレステロールを下げます。ビタミン類やカロチンは動脈硬化を防ぎます。適量の果物、イモ類、緑黄食野菜はおすすめです。また、中性脂肪は、甘いもの(果物や砂糖)やアルコールの過剰摂取が問題となります。これらを適量にして動脈硬化を予防しましょう。
脳神経外科の外来診療の内容も、世の中の高齢化の影響を受け、以前は頭痛の患者さんが大半を占めていましたが、最近は年々めまい症の患者さんの割合が増加しています。めまい症には、回転性のめまいと非回転性のめまい(フラツキ感と同じ意味)の二つがあり、いずれの症状も大きな意味でめまい症と呼ばれています。
このめまい症には、生命に危険を及ぼす様な脳腫瘍や脳卒中が直接原因のものと、そうでないものがあります。 今回後者の日常診察時によく見かけるめまい症について述べたいと思います。
めまい症の研究において、脳の左右の側頭葉に一つずつ体の位置を把握する中枢(頭位認識中枢)がある事がわかっています(成富、2009)。この中枢は、絶えず左右の間で連絡を取り合って体の位置の把握をしているようです。高齢者になると、この左右の連絡の速度が脳に虚血性の変化が起こっているために遅くなります。それに加えて疲れがたまったり、睡眠不足の時には更に連絡速度が遅くなる事でめまい症が起こると考えられています。このめまい症の頻度は60歳以上で約30%程度に起こると言われています。
このため、脳の精密検査で異常のないめまい症の場合は、老化の一症状であり、その対処法としては、睡眠不足を起こさない事や根を詰めて細かい作業を長時間しない事等を守って頂く事が大切です。
脳動脈瘤は主に脳の主幹動脈の分岐部にでき、破裂するとくも膜下出血を起こします。動脈瘤の大きさがどの位になれば破裂するかはまだ充分に解明されてませんが長径が5~7mm大以上で破裂する危険性が高まると考えられています。
脳動脈瘤は解剖や色々な統計から全人口の約5%程度つまり日本では500万人の方が持っておられると考えられています。又年間のくも膜下出血の患者さんの頻度は10万人に対して約20人、つまり日本では1億人に2万人の発症数と言われています。この数と前記の数とは考慮すると500万人に対して2万人が毎年破裂する計算です。つまり1000人で4人=0.4%の破裂率があります。ですからたとえ未破裂脳動脈瘤をMRIで指摘されても1年間で0.4%の破裂率ですから平均寿命に対する患者さんの年齢を考慮して手術が安全か経過観察が安全かをよく考える事が重要です。
また経過観察する場合は喫煙、高血圧症、過度の飲酒が破裂率を高めると言う報告があり注意が必要です。
脳卒中*の危険因子には、加齢や遺伝的素因など予防が不可能なものと、高血圧症、糖尿病、高脂血症、痛風等の生活習慣病や飲酒、喫煙等の予防が可能な因子があります。糖尿病の予防には定期的な運動習慣、食物繊維の摂取、脂肪摂取の抑制が重要す。 *脳梗塞、脳内出血、クモ膜下出血の総称
②糖尿病と食事
糖尿病とは、食事の量が多く、運動不足の為に血糖値が上昇しているにも関わらず、膵臓から出るインスリンが効率的に使われず、膵臓に負担がかかり、結果として血液中に糖分が余っている状態です。この血液中の余分な糖分が悪影響を引き起こします。具体的には微小血管炎を起こす事で、脳梗塞、心筋梗塞、網膜症、腎不全、末梢神経障害の危険性が高まります。
食事療法のポイントは、1度にたくさんの量の食事は控えて、腹八分目を心がけ膵臓に過度の負担をかけないようにする事です。具体的には、食事量を3食同じくらいに分けて摂取します。朝食を多めにして、昼と夜と食事を少なくします。朝食を抜くと、体が飢えに備えて脂肪を蓄積しようとし、肥満の原因になります。また、ながら食いは結果的に食べ過ぎになります。更に、早食いやまとめ食いも良くない事です。ゆっくりよくかんで食べましょう。
食品もGI値(グリセミックインデックス=ブトウ糖を100とした時の、食物100gあたりの血糖上昇率)の低いものを選ぶ知識を持ちましょう。主食では、高い順からパン>白米>パスタの順です。
また野菜を多めに取る様にしたいですが、最近の傾向として、御飯よりおかずを多く取りすぎる傾向にあるようですから、副食は1食1皿として、御飯(適量)を食べるようにして下さい。蛋白質は、魚や大豆、脂身の少ない肉からとりましょう。脂肪の摂取は動物性脂肪を減らし、植物性脂肪や魚から取りましょう。油を使った料理は1日2品までとしましょう。
お菓子や飲酒も控え目にして下さい。低脂肪の牛乳や適量の果物は食事と一緒にとらず、間食で摂取して空腹感の緩和に努めて下さい。外食などでは食べ残す勇気も必要です。定食やどんぶり物は御飯を1/3ほど残して下さい。
追記ー運動療法は、毎日6000歩~8000歩歩く事が理想です。